ハクビシン対策を習慣化するには?【日々の点検が重要】簡単にできる5つの日常的予防法

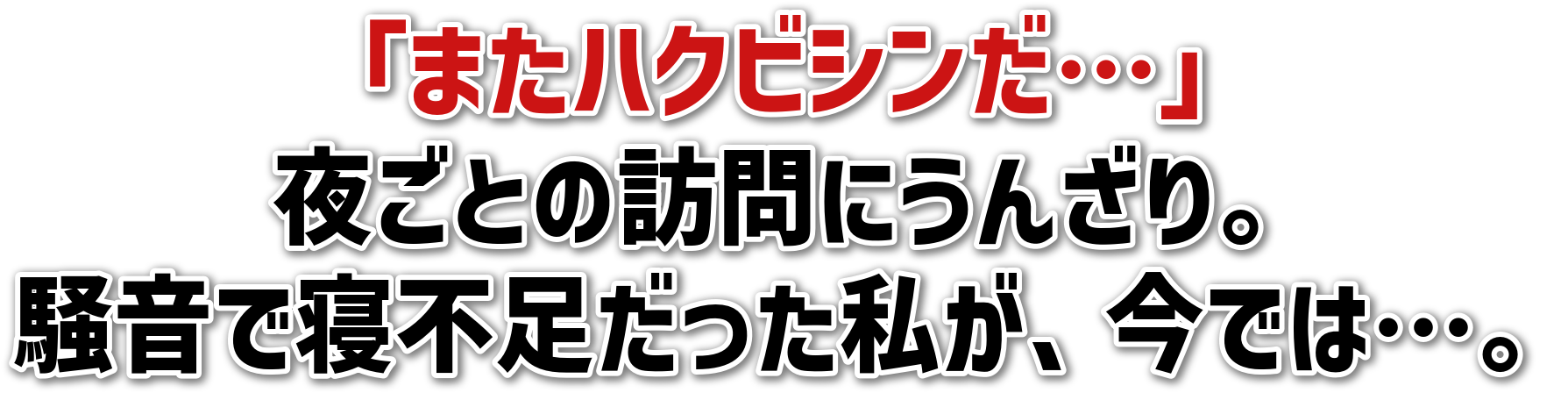
【この記事に書かれてあること】
ハクビシン対策、やってはみたものの続かない…。- ハクビシン対策の習慣化が重要
- 朝夕2回の点検で侵入口・餌・痕跡をチェック
- 家族全員で役割分担し意識を共有
- 季節ごとの対策を理解し実践
- 効果的な餌管理方法を選択
- 簡単な裏技で継続的な対策を実現
そんな経験ありませんか?
実は、対策の習慣化こそが被害撃退の決め手なんです。
でも、どうすれば続けられるの?
本記事では、誰でも簡単に実践できる5つの裏技をご紹介します。
朝夕の点検ルーティンから、家族で楽しむゲーム感覚の対策まで、継続のコツが満載。
さあ、一緒にハクビシンフリーの快適な暮らしを手に入れましょう!
【もくじ】
ハクビシン対策を習慣化する重要性と基本ステップ

日々の点検ルーティンで「侵入口」「餌」「痕跡」をチェック!
ハクビシン対策の基本は、毎日の点検にあります。侵入口、餌、痕跡の3つをチェックすることで、被害を大幅に減らせるんです。
まず、侵入口のチェック。
家の周りをぐるっと一周して、小さな隙間や穴がないか確認します。
「えっ、こんな小さな隙間から入れるの?」と思うかもしれませんが、ハクビシンは体を平らにして4〜5センチの隙間さえあれば入り込めちゃうんです。
屋根裏や換気口、配管の周りなどを特に念入りにチェックしましょう。
次に餌のチェック。
ハクビシンは果物や野菜が大好物。
庭に落ちた果物や、収穫し忘れた野菜はないですか?
生ゴミの管理も重要です。
「ちょっとくらい大丈夫」と外に放置していると、それが餌になってハクビシンを呼び寄せてしまいます。
最後に痕跡のチェック。
フンや足跡、かじり跡などを探します。
これらの痕跡を見つけたら、ハクビシンが活動していた証拠。
早めの対策が必要です。
- 侵入口チェック:隙間や穴がないか確認
- 餌チェック:落果や生ゴミの放置に注意
- 痕跡チェック:フン、足跡、かじり跡を探す
「面倒くさい」と思うかもしれませんが、被害が大きくなってからでは遅いんです。
毎日のちょっとした習慣が、大きな安心につながりますよ。
朝夕2回の点検が効果的「特に夕方が重要」
ハクビシン対策の点検は、朝と夕方の2回行うのが効果的です。特に夕方の点検が重要なんです。
なぜなら、ハクビシンは夜行性だからです。
朝の点検では、夜中にハクビシンが活動した痕跡を見つけることができます。
フンや足跡、かじられた跡など、新鮮な痕跡を発見できる可能性が高いんです。
「おや?昨日はなかったのに」という変化に気づきやすいのが朝の点検のメリット。
でも、本当に大切なのは夕方の点検なんです。
ハクビシンは日没後2〜3時間が最も活発になります。
夕方の点検で、ハクビシンが活動を始める前に対策を打つことができるんです。
例えば、庭に落ちている果物を片付けたり、ゴミ箱の蓋をしっかり閉めたり。
「ちょっと待って、夕方って忙しいんじゃない?」と思うかもしれません。
でも、たった5分でいいんです。
5分の点検で、一晩中安心して過ごせるんですよ。
- 朝の点検:夜間の活動痕跡を確認
- 夕方の点検:ハクビシンの活動前に対策
- 5分でOK:短時間でも効果大
夕方も、夕食の買い物から帰ってきたついでに庭を一周するだけでいいんです。
この小さな習慣が、大きな安心につながりますよ。
家族で役割分担!スマホのリマインダーで忘れず継続
ハクビシン対策を継続するコツは、家族で役割分担すること。そして、スマートフォンのリマインダー機能を活用すれば、忘れずに続けられるんです。
まず、家族で話し合って役割を決めましょう。
例えば、こんな感じです。
- お父さん:庭の点検と侵入口のチェック
- お母さん:生ゴミの管理と果樹の収穫
- 子どもたち:フンや足跡の確認
でも、これが大切なんです。
家族全員で取り組むことで、意識が高まり、継続しやすくなります。
次に、スマートフォンのリマインダー機能を使います。
毎日決まった時間に「ハクビシン対策の時間だよ」とお知らせが来るように設定しましょう。
「あ、そうだった!」と思い出せるんです。
さらに、家族のグループチャットを作って、対策の報告をし合うのもおすすめ。
「今日は庭に落ち葉がたくさんあったよ。ハクビシンの隠れ場所になりそうだから掃除したよ」「玄関前にフンらしきものを見つけたから、写真撮ったよ」など、情報共有することで、家族全員の意識が高まります。
この方法なら、忘れずに続けられるだけでなく、家族の絆も深まるんです。
「ハクビシン対策」が、家族の共通の目標になるんですよ。
ちょっとした工夫で、面倒な対策も楽しく続けられるんです。
餌となる生ゴミと果樹の管理が最重要ポイント!
ハクビシン対策で最も重要なのは、餌の管理です。特に注意すべきは生ゴミと果樹。
これらをしっかり管理すれば、ハクビシンを寄せ付けない環境が作れるんです。
まず生ゴミ。
ハクビシンは嗅覚が鋭く、生ゴミの匂いを遠くからも感知します。
「え?ゴミ箱の中なら大丈夫じゃないの?」と思うかもしれませんが、それが間違いなんです。
生ゴミは必ず密閉容器に入れましょう。
匂いが漏れないよう、蓋はしっかりと閉めることが大切です。
次に果樹の管理。
ハクビシンは果物が大好物。
庭に果樹がある場合は要注意です。
- 落果はすぐに拾う
- 熟した果実は早めに収穫する
- 木に残った果実にはネットをかける
「でも、毎日チェックするのは大変…」と思うかもしれません。
そこで、ちょっとしたコツを紹介します。
夕食の準備をする前に、庭を一周するだけでいいんです。
「今日のサラダの具を取りに行こう」と思って庭に出れば、自然と果樹や落果のチェックができちゃいます。
また、コンポストを使っている場合は注意が必要です。
生ゴミの堆肥化は環境にやさしい取り組みですが、ハクビシンを引き寄せる原因にもなります。
コンポストには必ずフタをし、周りに金網を設置するなどの工夫が必要です。
この「餌管理」を徹底することで、ハクビシンの来訪を大幅に減らせるんです。
小さな習慣が、大きな効果を生み出すんですよ。
「○○はやっちゃダメ!」対策を一時的にしか行わない
ハクビシン対策で絶対にやってはいけないのが、対策を一時的にしか行わないこと。「一度やったから大丈夫」という考えは、とても危険なんです。
ハクビシンは賢い動物。
一度追い払っても、餌や住みやすい環境があれば必ず戻ってきます。
「えっ、そんなしつこいの?」と驚くかもしれません。
でも、これがハクビシンの生態なんです。
よくある失敗例を見てみましょう。
- 侵入口を一度塞いだら安心してしまう
- 忌避剤を置いたら効果が永続すると思い込む
- 数日間ハクビシンが来なかったから対策をやめる
なぜなら、ハクビシンは新しい侵入口を見つけたり、忌避剤の効果が切れるのを待っていたりするからです。
じゃあ、どうすればいいの?
答えは簡単。
対策を習慣化することです。
毎日の点検、餌の管理、環境整備を続けることが大切なんです。
「でも、毎日なんて面倒くさい…」と思うかもしれません。
でも、考えてみてください。
歯磨きだって毎日やりますよね?
それと同じなんです。
最初は面倒に感じても、習慣になれば自然とできるようになるんです。
ハクビシン対策は、まるでいたちごっこ。
でも、あなたが諦めなければ、必ず勝てるんです。
一時的な対策ではなく、継続的な取り組みが重要。
これを忘れずに、毎日少しずつ対策を続けていきましょう。
そうすれば、ハクビシンフリーの快適な暮らしが待っているはずです。
季節ごとの対策と家族全員での意識共有で習慣化
春は繁殖期!巣作り場所の封鎖を徹底
春はハクビシンの繁殖期です。巣作り場所の封鎖を徹底することが、この季節の対策の要となります。
「え?春になるとハクビシンが子育てを始めるの?」そうなんです。
ハクビシンは春と秋の年2回、繁殖期を迎えます。
特に春は、冬を越した後の大切な時期。
家の中に巣を作られたら大変なことになっちゃいます。
では、どんなところを重点的にチェックすればいいのでしょうか?
- 屋根裏や天井裏の隙間
- 壁の中の空洞
- 床下のすき間
- 物置や倉庫の隅
- 庭の生け垣や茂みの中
「でも、どうやって封鎖するの?」簡単です。
金網や板で塞いだり、隙間にはコーキング材を詰めたりするんです。
ポイントは、小さな隙間も見逃さないこと。
ハクビシンは体を平らにして、わずか4〜5センチの隙間からも侵入できるんです。
「えー!そんな小さな隙間から入れるの?」驚きですよね。
だからこそ、丁寧なチェックが必要なんです。
春の対策を習慣化するコツは、桜の開花をきっかけにすること。
「あ、桜が咲いた!ハクビシンチェックの時期だ!」と思い出せます。
毎年の恒例行事として、家族みんなで取り組めば、楽しみながら対策ができますよ。
これで春のハクビシン対策はばっちり。
子育てを始めるハクビシンたちに、「ごめんね、ここは貸せないよ」とやんわりお断りできるわけです。
夏は果樹の収穫管理と水場の点検清掃が重要
夏のハクビシン対策で特に大切なのは、果樹の収穫管理と水場の点検清掃です。この2つを日課にすることで、ハクビシンを寄せ付けない環境づくりができるんです。
まず、果樹の収穫管理について。
夏は果物がたくさん実る季節。
ハクビシンにとっては、まさに「ごちそう」の季節なんです。
「えっ、ハクビシンって果物好きなの?」そうなんです。
特に甘い果物が大好物なんですよ。
では、具体的にどんなことに気をつければいいでしょうか?
- 熟した果実はすぐに収穫する
- 落果はその日のうちに拾う
- 木に残った果実にはネットをかける
- 収穫時期を迎えた木の周りは特に注意深く見回る
「毎日なんて面倒くさい…」と思うかもしれません。
でも、考えてみてください。
毎日の食事の材料を取りに行くような感覚で庭に出れば、そんなに大変ではありませんよ。
次に、水場の点検清掃です。
夏は暑いので、ハクビシンも水を求めてやってきます。
庭の池や水たまり、ペットの水飲み場などが、ハクビシンを引き寄せる原因になっているかもしれません。
水場の管理のポイントは以下の通りです:
- 不要な水たまりをなくす
- 池の周りに柵を設置する
- ペットの水は夜間は室内に置く
- 雨樋や排水溝をこまめに掃除する
でも、水場は単なる水飲み場ではなく、ハクビシンにとっては快適な生活スポットになるんです。
だからこそ、しっかり管理する必要があるんですね。
この夏の対策、ぜひ試してみてください。
きっと、ハクビシンとの「かくれんぼ」に勝てるはずです!
冬に向けて建物の隙間チェックと補修を習慣化
冬に向けてのハクビシン対策で最も重要なのは、建物の隙間チェックと補修を習慣化することです。寒さが厳しくなるにつれ、ハクビシンは暖かい場所を求めて家屋に侵入しようとします。
そのため、秋から冬にかけて、こまめなチェックと補修が欠かせません。
「えっ、冬でもハクビシンは活動するの?」そう思った方も多いのではないでしょうか。
実は、ハクビシンは冬眠しないんです。
寒さをしのぐため、むしろ積極的に暖かい場所を探します。
そして、その暖かい場所が…そう、みなさんの家なんです!
では、どんなところをチェックすればいいのでしょうか?
- 屋根と壁の接合部
- 窓やドアの周り
- 配管やケーブルの貫通部
- 換気口や通気口
- 軒下や破風板の隙間
「でも、そんなの大変じゃない?」と思うかもしれません。
ここで、ちょっとしたコツをお教えしましょう。
冬支度の一環として隙間チェックを習慣化するのです。
例えば、こたつを出すときや、冬物の衣類を出すときなど、季節の変わり目の作業と一緒に行えば、自然と習慣になりますよ。
補修方法も簡単です。
小さな隙間なら市販のコーキング材で、大きめの隙間なら金網や板で塞ぎます。
「ん?それって難しそう…」と思った方、安心してください。
ホームセンターで売っている材料を使えば、ちょっとした日曜大工気分で楽しみながらできますよ。
この習慣化のコツは、家族で協力すること。
「パパは屋根裏、ママは1階、子どもたちは庭を担当」なんて具合に分担すれば、楽しみながらできるはずです。
冬の前にしっかり対策をしておけば、寒い季節もハクビシンの心配なく、ぬくぬくと過ごせます。
さあ、今年の冬は、ハクビシンに「ごめんね、満室なんだ」って言えるようにしましょう!
週1回の「ハクビシン対策会議」で家族の意識を高める
ハクビシン対策を家族全員で習慣化するには、週1回の「ハクビシン対策会議」がとても効果的です。この会議で情報を共有し、対策のアイデアを出し合うことで、家族全員の意識が高まり、継続的な対策が可能になるんです。
「えっ、会議なんてかた苦しそう…」なんて思った方、心配いりません。
この会議、硬い雰囲気じゃなくて、わいわいがやがやの楽しい家族団らんなんです。
では、具体的にどんなことを話し合えばいいのでしょうか?
ここでいくつかのポイントをご紹介します。
- 今週見つけたハクビシンの痕跡を報告
- 効果があった対策方法の共有
- 新しい対策アイデアのブレインストーミング
- 来週の対策計画の立案
- 家族それぞれの役割の確認と調整
会議を楽しくする工夫も大切です。
例えば、「今週のハクビシンハンター賞」を設けて、一番がんばった人を表彰するのはどうでしょう?
「わぁ、ママが見つけた足跡、すごいね!」「パパの仕掛けたアラーム、よく効いたね!」なんて声が飛び交えば、みんなのやる気もぐんぐん上がります。
また、会議の時間を決めておくのもおすすめです。
例えば、毎週日曜日の夕食後30分と決めれば、自然と習慣になります。
「あ、もうすぐハクビシン会議の時間だ!」と家族で声を掛け合える、そんな光景が目に浮かびますね。
もちろん、真剣に話し合うことも大切です。
でも、あまり肩肘張らずに、家族の絆を深める機会として楽しんでください。
ハクビシン対策が、家族の共通の目標になれば、それはそれで素敵なことですよね。
さあ、今週末から「ハクビシン対策会議」、始めてみませんか?
きっと、ハクビシンとの知恵比べに、家族全員で楽しく取り組めるはずです!
子どもも参加!ゲーム感覚で学べるクイズやカードで楽しく
ハクビシン対策を家族全員の習慣にするには、子どもたちの参加が欠かせません。そこで効果的なのが、ゲーム感覚で学べるクイズやカードゲーム。
楽しみながらハクビシンについて学び、対策意識を高められるんです。
「え?ハクビシンのゲーム?」と思われるかもしれませんね。
でも、これが意外と面白いんです。
子どもたちの好奇心をくすぐりながら、大切な知識を身につけられる、まさに一石二鳥の方法なんです。
では、具体的にどんなゲームができるでしょうか?
いくつかアイデアをご紹介します。
- ハクビシンクイズ大会:ハクビシンの生態や習性に関するクイズを出し合います。
- ハクビシン対策カルタ:「は」のハクビシン、「く」の空き缶アラーム、など対策にまつわる言葉でカルタを作ります。
- ハクビシンすごろく:マスにハクビシン対策のヒントを書き込んだすごろくを作って遊びます。
- ハクビシン探偵団:庭を探検して、ハクビシンの痕跡を見つけるゲームをします。
- ハクビシン対策カードバトル:対策方法を書いたカードで、どちらがより効果的か競い合います。
「わぁ、ハクビシンってこんなに賢いんだ!」「この対策、面白そう!」なんて声が聞こえてきそうですね。
ポイントは、ゲームを通じて学んだことを実際の対策に活かすことです。
例えば、クイズで正解したら、その対策を実践する係になるとか。
カルタで一番多く取れた人が、次の週の対策リーダーになるとか。
そうすれば、ゲームと実践がつながり、より効果的な習慣化ができます。
また、これらのゲームを作る過程自体も、家族の絆を深める良い機会になります。
「パパ、このクイズ難しすぎない?」「ママ、このカードのイラスト、上手!」なんてやりとりをしながら、家族で協力して作り上げていく。
その過程が、実は一番の「対ハクビシン作戦」かもしれませんね。
さあ、今度の週末は、家族みんなでハクビシンゲーム大会を開いてみませんか?
きっと、笑顔いっぱいの楽しい時間になるはずです。
そして、その笑顔がハクビシン対策の大きな力になるんです。
「よーし、みんなで頑張ろう!」そんな家族の姿が目に浮かびますね。
効果的な習慣化のコツと驚きの裏ワザ

密閉容器vs堆肥化「生ゴミ管理はどちらが効果的?」
ハクビシン対策の生ゴミ管理では、密閉容器の使用が堆肥化よりも効果的です。匂いの漏れを防ぎ、ハクビシンを寄せ付けない環境づくりに役立ちます。
「えっ?堆肥化って環境にいいんじゃないの?」そう思った方も多いでしょう。
確かに堆肥化は環境に優しい取り組みです。
でも、ハクビシン対策としては要注意なんです。
なぜかというと、堆肥化の過程で発生する匂いがハクビシンを引き寄せてしまうんです。
「うわっ、おいしそうな匂いがする!」とハクビシンが寄ってきちゃうわけです。
一方、密閉容器を使うメリットは以下の通りです:
- 匂いが外に漏れない
- ハクビシンが中身を見られない
- 虫や他の動物も寄りつかない
- 衛生的に保管できる
大丈夫です。
使い方は簡単ですよ。
密閉容器の上手な使い方をいくつかご紹介します:
- 蓋つきのプラスチック容器を用意する
- 生ゴミを入れたら必ず蓋をする
- 容器は屋内か、ハクビシンの手の届かない場所に置く
- こまめに中身を捨てる
- 使用後は洗浄して乾かす
「よし、これなら続けられそう!」という気持ちになりませんか?
ただし、注意点もあります。
密閉容器を使っても、長期間放置すると匂いが漏れる可能性があります。
こまめな処理を心がけましょう。
こうした対策を続けていけば、ハクビシンに「ごめんね、ここにはおいしいものないよ」と言えるような環境が作れるはずです。
さあ、今日から密閉容器でハクビシン対策、始めてみませんか?
果樹管理は「ネット被覆vs早期収穫」どちらが労力対効果◎?
果樹管理におけるハクビシン対策では、早期収穫が労力対効果で優れています。ネット被覆よりも手間がかからず、収穫物の品質も保てるため、習慣化しやすい方法なんです。
「えっ、ネットをかけないの?」と驚く方もいるでしょう。
確かに、ネット被覆も効果的な方法の一つです。
でも、毎日の習慣として考えると、早期収穫のほうが続けやすいんです。
では、早期収穫のメリットを見てみましょう:
- ハクビシンに先手を打てる
- 収穫物の品質管理がしやすい
- 毎日の作業が簡単
- ネット購入のコストがかからない
- 見た目も自然なまま
大丈夫です。
ちょっとしたコツがあるんです。
早期収穫を成功させるポイントをいくつかご紹介します:
- 果実の色づきを毎日チェック
- 触ってみて、少し柔らかくなったら収穫のサイン
- 収穫後は室内で追熟させる
- 品種ごとの適切な収穫時期を覚える
- 天候や気温の変化にも注意を払う
「へえ、こんな方法があったんだ!」と新しい発見があったのではないでしょうか。
早期収穫を習慣化するコツは、毎日の散歩や庭の手入れのついでに果樹をチェックすること。
「今日はどんな実が色づいてるかな?」とわくわくしながら見て回れば、苦にならずに続けられますよ。
この方法なら、ハクビシンに「ごめんね、一足遅かったみたい」と言えるはずです。
さあ、明日から早期収穫でハクビシンに勝つ、新しい習慣を始めてみませんか?
ペットフード「屋内保管vs蓋付き容器の屋外保管」効果比較
ペットフードの管理では、屋内保管が蓋付き容器の屋外保管よりも効果的です。匂いの漏れを完全に防ぎ、ハクビシンを引き寄せる原因を根本から断つことができるんです。
「えっ、蓋付きの容器じゃダメなの?」と思われた方も多いでしょう。
確かに、蓋付き容器も一定の効果はあります。
でも、完璧とは言えないんです。
なぜ屋内保管がおすすめなのか、理由を見てみましょう:
- 匂いが外に一切漏れない
- ハクビシンの目に触れない
- 雨や湿気から守れる
- 虫や他の動物の侵入も防げる
- ペットフードの鮮度が長持ちする
大丈夫です。
うまく保管するコツがあるんです。
屋内でのペットフード保管のポイントをいくつかご紹介します:
- 密閉性の高い容器を使用する
- 涼しく乾燥した場所に置く
- 日光が当たらない場所を選ぶ
- 定期的に容器を清掃する
- 使用時以外は必ず蓋を閉める
「なるほど、これならできそう!」という気持ちになりませんか?
屋内保管を習慣化するコツは、ペットの餌やり時間に合わせて保管場所を決めること。
例えば、「朝晩の餌やりの時だけキッチンに出す」といった具合です。
そうすれば、自然とリズムができて続けやすくなりますよ。
この方法なら、ハクビシンに「ごめんね、おいしそうな匂いはもうしないよ」と言えるはずです。
さあ、今日からペットフードの屋内保管、始めてみませんか?
きっと、ハクビシン対策の大きな一歩になりますよ。
空き缶アラームで早期発見!簡単自作の侵入警報装置
ハクビシン対策の裏技として、空き缶アラームがおすすめです。簡単に自作でき、侵入を早期に発見できる優れものなんです。
「空き缶アラーム?なんだそれ?」と思われたでしょう。
実は、とってもシンプルな仕組みなんです。
空き缶に小石を入れて、ハクビシンの侵入経路に設置するだけ。
ハクビシンが触れると、ガラガラと音が鳴って知らせてくれるんです。
この空き缶アラームの魅力をいくつか挙げてみましょう:
- 材料費はほぼゼロ
- 誰でも簡単に作れる
- 設置場所を自由に変えられる
- 電気を使わないので安全
- 環境にやさしい
では、作り方と使い方をご紹介しましょう。
空き缶アラームの作り方と使い方
- 空き缶を洗って乾かす
- 小さな石を5〜10個入れる
- 缶の上部に紐を通して吊るせるようにする
- ハクビシンの侵入しそうな場所に設置する
- 夜間に音がしたら要注意!
本当に、子どもでも作れるくらい簡単なんです。
この空き缶アラーム、実は家族で作るのも楽しいんですよ。
「パパ、この缶はどう?」「ママ、この石ちょうどいいかな?」なんて会話しながら作れば、家族の絆も深まります。
ただし、注意点もあります。
強風の日は誤報が出やすいので、設置場所には気を付けましょう。
また、近所迷惑にならないよう、音の大きさにも配慮が必要です。
この裏技で、ハクビシンに「ごめんね、もう忍び込めないよ」と言わせちゃいましょう。
さあ、今日から空き缶アラームでハクビシン対策、始めてみませんか?
きっと、新しい発見があるはずですよ。
古いスマホで監視カメラに!ハクビシンの行動パターンを把握
ハクビシン対策の裏技として、古いスマートフォンを活用した監視カメラがとても効果的です。ハクビシンの行動パターンを把握でき、的確な対策を立てられるんです。
「えっ、古いスマホがカメラになるの?」と驚いた方も多いでしょう。
実は、無料のアプリを使えば簡単に監視カメラに変身させられるんです。
しかも、新しいカメラを買うよりずっと経済的!
この方法のメリットをいくつか挙げてみましょう:
- コストがほとんどかからない
- 設置場所を自由に変えられる
- 映像を記録できる
- 遠隔で確認できる
- 動体検知機能で必要な映像だけ記録
では、具体的な使い方をご紹介します。
古いスマホで監視カメラを作る手順
- 無料の監視カメラアプリをダウンロード
- アプリの設定を行う(動体検知をオンにするのがおすすめ)
- スマホを電源に繋ぎ、ハクビシンが来そうな場所に設置
- 別のスマホやパソコンから映像を確認
- 記録された映像を分析し、ハクビシンの行動パターンを把握
本当に、ちょっとした設定だけで始められるんです。
この方法の面白いところは、まるで探偵になったような気分を味わえること。
「昨日の夜9時にハクビシンが来たぞ!」「あ、今日は2匹で来てる!」なんて、家族で映像を見ながらわいわい盛り上がれますよ。
ただし、注意点もあります。
カメラの向きには気を付け、近所のプライバシーを侵害しないようにしましょう。
また、防水対策も忘れずに。
雨に濡れてスマホが壊れたら元も子もありません。
この裏技で、ハクビシンに「ごめんね、もう秘密の行動なんてできないよ」と言わせちゃいましょう。
さあ、今日から古いスマホで監視カメラ作り、始めてみませんか?
きっと、ハクビシン対策の新しい扉が開けるはずですよ。