ハクビシンからスイカを守るには?【ネットカバーが効果的】収穫を確保する3つの方法

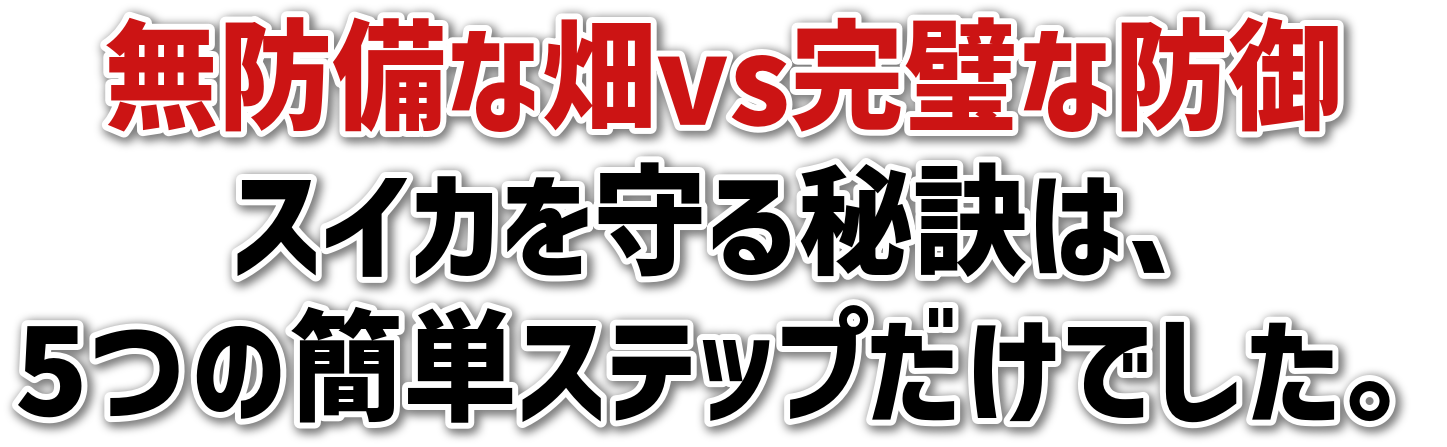
【この記事に書かれてあること】
大切に育てたスイカがハクビシンに食べられてしまう…。- ネットカバーの設置でハクビシンの侵入を物理的に阻止
- 電気柵や忌避剤を併用してより強力な防御ラインを構築
- スイカの栽培方法や品種選びで被害リスクを軽減
- 収穫時期の調整でハクビシンの食害を回避
- 囮作物や音・光・匂いを利用した意外な対策方法も効果的
そんな悲しい経験をした方も多いのではないでしょうか?
でも、諦めないでください!
実は、ハクビシンからスイカを守る方法はたくさんあるんです。
この記事では、ネットカバーを中心とした5つの簡単対策を紹介します。
これらの方法を組み合わせれば、被害を劇的に減らすことができます。
さあ、一緒にハクビシン対策を学んで、今年こそは自慢のスイカを収穫しましょう!
【もくじ】
ハクビシンからスイカを守る効果的な方法とは

ネットカバーの設置で「侵入阻止」を実現!
ネットカバーの設置は、ハクビシンからスイカを守る最も効果的な方法です。目の細かい丈夫なネットを使えば、ハクビシンの侵入をしっかり防げます。
まず、ネットの選び方が重要です。
目合いが2〜3センチの丈夫なポリエチレン製のネットがおすすめです。
このサイズならハクビシンが通り抜けられません。
「えっ、そんな小さな隙間でも通れるの?」と思うかもしれませんが、ハクビシンは意外と体をくねらせて小さな隙間を通り抜けるんです。
ネットの設置高さは、地上から1.5〜2メートルくらいが適切です。
ハクビシンは驚くほどジャンプ力があるので、低すぎると飛び越えられちゃいます。
「ピョーン」っと軽々と越えてしまうので要注意です。
設置する際のポイントは3つあります。
- 地面との隙間をなくすこと
- 支柱をしっかり固定すること
- ネットに緩みがないようにピンと張ること
「よーし、完璧に設置したぞ」と思っても、翌朝見てみると「あれ?どこから入ったの?」なんてことになりかねません。
ネットの耐久性を高めるコツもあります。
紫外線対策済みのものを選び、使わない時期は屋内で保管しましょう。
また、定期的に点検して破れや緩みがないか確認することが大切です。
こまめなケアで長持ちさせれば、毎年の対策費用も抑えられますよ。
電気柵の活用で「強力な防御ライン」を構築
電気柵は、ハクビシンを寄せ付けない強力な防御ラインを作り出します。ネットカバーと併用すれば、さらに効果的な対策になります。
電気柵の設置方法は簡単です。
地上から約15〜20センチの高さに2〜3段設置します。
ハクビシンの体格を考えると、この高さが最も効果的なんです。
「ビリッ」とした軽い電気ショックでハクビシンを寄せ付けません。
電圧は4000〜6000ボルトに設定するのがおすすめです。
これくらいの電圧なら、ハクビシンに危害を加えることなく、効果的に撃退できます。
「え?そんな高電圧で大丈夫なの?」と心配になるかもしれませんが、実は電流量が少ないので安全なんです。
電気柵を設置する際の注意点は3つあります。
- 雑草が触れないよう、こまめな草刈りをすること
- 雨天時の漏電に注意すること
- 定期的にバッテリーの点検をすること
「あれ?昨日まで効いていたのに」なんてことにならないよう、こまめなメンテナンスが大切です。
電気柵の周りには、警告の看板を立てるのも忘れずに。
人や家畜が誤って触れないようにしましょう。
「ピリッ」としたショックを受けても大丈夫ですが、びっくりするかもしれませんからね。
忌避剤の使用で「ハクビシンを寄せ付けない環境」作り
忌避剤を使えば、ハクビシンが嫌がる匂いでスイカ畑を守れます。ネットや電気柵と組み合わせれば、さらに強力な防御網が完成します。
忌避剤には大きく分けて3種類あります。
化学合成型、天然成分型、音響型です。
それぞれ特徴があるので、畑の環境に合わせて選びましょう。
「どれがいいんだろう?」と迷ったら、まずは天然成分型から試してみるのがおすすめです。
天然成分型の忌避剤には、こんな利点があります。
- 環境への影響が少ない
- 人体に安全
- 長期使用しても耐性ができにくい
「ふんっ、こんな臭いところには近づかないぞ」とハクビシンも考えるわけです。
忌避剤の使い方のコツは、畑の周囲に散布することです。
スイカに直接かけるのではありません。
雨が降った後や2〜3週間ごとに再散布するのを忘れずに。
「一度撒いたらOK」と油断していると、効果が薄れてハクビシンに侵入されちゃいますよ。
忌避剤の効果を最大限に引き出すには、複数の種類を組み合わせるのがおすすめです。
匂いだけでなく、音や光を使った忌避剤も併用すれば、ハクビシンを寄せ付けない強力な環境が作れます。
「これでもか!」というくらい対策を重ねれば、ハクビシンも「ここは諦めよう」と思うはずです。
スイカ畑の周囲に「バリア植物」を植えて対策
スイカ畑の周りに特定の植物を植えることで、ハクビシンの侵入を防ぐ「生きたバリア」を作れます。これは自然な方法で、環境にも優しい対策なんです。
効果的なバリア植物には、こんなものがあります。
- ラベンダー
- ミント
- マリーゴールド
- ニーム
- ローズマリー
「うわっ、くさい!」とハクビシンが思わず後ずさりしてしまうわけです。
特にミントは効果的です。
ミントの香りは私たち人間には爽やかで心地よいものですが、ハクビシンにとっては「ムッ」とする不快な匂いなんです。
スイカ畑の周りにミントを植えれば、天然の忌避剤として働きます。
バリア植物を植える際のポイントは、スイカ畑を囲むように配置することです。
隙間なく植えれば植えるほど効果的です。
「よーし、完璧な緑のバリアだ!」と思えるくらい、ぐるりと囲んでしまいましょう。
ただし、注意点もあります。
バリア植物が大きくなりすぎると、スイカの生育に影響を与える可能性があります。
定期的に剪定して、適度な大きさを保つことが大切です。
「うっかり忘れてたら、ジャングルみたい!」なんてことにならないよう気をつけましょう。
バリア植物は見た目にも美しく、畑の景観を向上させる効果もあります。
「ハクビシン対策しながら、畑が素敵になった!」一石二鳥の効果が得られますよ。
ハクビシン対策を怠ると「全滅の危機」に!
ハクビシン対策をしっかり行わないと、せっかく育てたスイカが全滅してしまう危険性があります。一度ハクビシンに狙われると、被害は急速に拡大していくんです。
ハクビシンの食欲は旺盛で、一晩でスイカ畑を荒らしつくすことも珍しくありません。
「昨日まで元気だったスイカが、朝起きたらめちゃくちゃに…」なんて悲劇が起こりかねないのです。
被害の進行は、こんな具合です。
- 最初は1〜2個のスイカにかじり跡
- 数日後には半数以上のスイカが食べられる
- 1週間もすれば、ほぼ全滅状態に
「ここにおいしいごちそうがあるぞ!」とハクビシン仲間に知らせてしまい、被害がどんどん拡大していくんです。
対策を怠ると、経済的な損失も深刻です。
スイカ栽培にかけた時間とお金が水の泡になってしまいます。
「今年の収入がゼロに…」なんて事態も起こりうるのです。
さらに厄介なのは、一度ハクビシンが居着いてしまうと、翌年以降も同じ場所に現れる可能性が高いことです。
「去年はおいしかったなあ、今年も来てみよう」とハクビシンが覚えてしまうんです。
だからこそ、早めの対策が重要なんです。
最初の兆候を見逃さず、すぐに行動を起こしましょう。
「今のうちに対策しておけば、安心してスイカ栽培を楽しめる」というわけです。
ハクビシン対策は、スイカ栽培の成功の鍵を握っているんですよ。
スイカの栽培方法とハクビシン被害の関係性
地這い栽培vs棚上げ栽培「被害リスクの差」を比較
スイカの栽培方法によって、ハクビシンの被害リスクに大きな差が出ることをご存知ですか?地這い栽培と棚上げ栽培では、被害の受けやすさが全然違うんです。
まず、地這い栽培から見ていきましょう。
地面に這わせて育てる従来の方法です。
「昔からこの方法でやってきたから」と思う方も多いかもしれません。
でも、実はこの方法、ハクビシンにとっては「いただきます!」状態なんです。
地這い栽培の問題点は3つあります。
- スイカが地面に直接触れているため、ハクビシンが見つけやすい
- 果実が低い位置にあるため、ハクビシンが簡単に近づける
- 地面の湿気で果実が傷みやすく、匂いが強くなってハクビシンを引き寄せる
地面から離して育てる方法です。
「え?スイカを棚で?」と驚く方もいるかもしれません。
でも、これがハクビシン対策にはバッチリなんです。
棚上げ栽培のメリットは以下の通りです。
- 果実が地面から離れているため、ハクビシンが見つけにくい
- 高い位置にあるため、ハクビシンが簡単に近づけない
- 風通しが良く果実が傷みにくいため、ハクビシンを引き寄せる匂いが抑えられる
「ちょっと面倒だけど、収穫量が増えるなら…」と考える方も多いはず。
実際、棚上げ栽培に切り替えて被害が激減したという声をよく聞きます。
ただし、棚上げ栽培にも注意点があります。
支柱をしっかり固定しないと、重みで倒れてしまう可能性があるんです。
「せっかく棚上げしたのに、台無し…」なんてことにならないよう、設置には気を付けましょう。
結論として、ハクビシン被害を減らしたいなら、棚上げ栽培への切り替えを強くおすすめします。
手間はかかりますが、その分の見返りは大きいはずです。
「今年こそはたくさん収穫するぞ!」という方、ぜひ試してみてください。
早生品種vs晩生品種「ハクビシンの食害頻度」の違い
スイカの品種選びで、ハクビシンの食害頻度を大きく左右できることをご存知でしょうか?早生品種と晩生品種では、被害の受けやすさが全然違うんです。
まず、早生品種について見ていきましょう。
早く収穫できる品種のことです。
「早く食べられるならいいじゃない」と思う方もいるでしょう。
実は、この早生品種がハクビシン対策には有効なんです。
早生品種のメリットは3つあります。
- 収穫時期が早いため、ハクビシンの活動が活発になる前に収穫できる
- 栽培期間が短いので、ハクビシンに見つかるリスクが低い
- 果実の香りが控えめなため、ハクビシンを引き寄せにくい
収穫までに時間のかかる品種です。
「じっくり育てた方が美味しいんじゃない?」と考える方もいるかもしれません。
でも、これがハクビシンにとっては「ごちそうさま!」状態になりやすいんです。
晩生品種の問題点は以下の通りです。
- 収穫時期が遅いため、ハクビシンの活動が活発な時期と重なる
- 栽培期間が長いので、ハクビシンに見つかるリスクが高い
- 果実の香りが強くなりやすく、ハクビシンを引き寄せやすい
「ちょっと小ぶりだけど、無事に収穫できるなら…」と考える方も多いはず。
実際、早生品種に切り替えて被害が激減したという声をよく聞きます。
ただし、早生品種にも注意点があります。
糖度が晩生品種より若干低くなる可能性があるんです。
「甘さが足りないよ…」なんてガッカリしないよう、栽培管理には気を付けましょう。
結論として、ハクビシン被害を減らしたいなら、早生品種への切り替えを強くおすすめします。
味の違いはありますが、その分収穫できる喜びは大きいはずです。
「今年こそは無事に収穫するぞ!」という方、ぜひ試してみてください。
大玉スイカvs小玉スイカ「被害の受けやすさ」を検証
スイカの大きさによって、ハクビシンの被害の受けやすさが変わってくるって知っていましたか?大玉スイカと小玉スイカでは、ハクビシンにとっての魅力度が全然違うんです。
まず、大玉スイカについて見ていきましょう。
「大きいスイカの方が美味しそう!」と思う人も多いはず。
でも、実はこの大玉スイカ、ハクビシンにとっては「重くて持ち帰れない…」という厄介な存在なんです。
大玉スイカがハクビシンに狙われにくい理由は3つあります。
- 重くて持ち運びが難しいため、その場で食べるしかない
- 皮が厚いので、簡単に中身にたどり着けない
- 一度に食べきれないので、効率が悪い
「小さいスイカなんて物足りないよ」と思う方もいるかもしれません。
でも、これがハクビシンにとっては「ちょうどいい!」サイズなんです。
小玉スイカがハクビシンに狙われやすい理由は以下の通りです。
- 軽くて持ち運びやすいため、安全な場所に持ち去れる
- 皮が薄いので、簡単に中身にたどり着ける
- 一度で食べきれるサイズなので、効率が良い
対策はあります。
小玉スイカを育てる場合は、ネットやフェンスでしっかり守ることが大切です。
「ガードを固めれば大丈夫」というわけです。
ただし、大玉スイカにも注意点があります。
ハクビシンが食べられないからといって安心はできません。
「がぶっ」とかじられて台無しになることもあるんです。
「せっかく大きく育ったのに…」なんてことにならないよう、やはり対策は必要です。
結論として、ハクビシン被害を減らしたいなら、大玉スイカの栽培をおすすめします。
ただし、完全に安全というわけではないので、他の対策と組み合わせるのがベストです。
「今年は大玉スイカにチャレンジしてみようかな」という方、ぜひ試してみてください。
きっと、ハクビシンとの知恵比べを楽しめるはずですよ。
スイカの香りと「ハクビシンの接近頻度」の相関関係
スイカの香りが強くなるほど、ハクビシンの接近頻度が高まるって知っていましたか?実は、スイカの香りとハクビシンの行動には深い関係があるんです。
まず、スイカの香りについて考えてみましょう。
「甘い香りがすると美味しそう!」と思いますよね。
でも、その香りこそがハクビシンを引き寄せる"罠"になっているんです。
スイカの香りがハクビシンを引き寄せる理由は3つあります。
- 甘い香りが餌の存在を知らせる目印になる
- 強い香りほど遠くからでも感知できる
- 香りの強さが熟度を示すため、食べ頃を判断できる
でも、それではスイカの美味しさが半減してしまいます。
香りと美味しさは切っても切れない関係なんです。
では、どうすればいいのでしょうか?
ここで大切なのは、香りの「管理」です。
完全に消すのではなく、ハクビシンに気づかれにくくする工夫が必要なんです。
香りを抑える方法はいくつかあります。
- スイカの周りに強い香りのハーブ(ミントやラベンダーなど)を植える
- 収穫直前にスイカを新聞紙で包む
- 防虫ネットで覆い、香りの拡散を防ぐ
「ちょっと手間はかかるけど、それだけの価値はある!」と思う方も多いはず。
ただし、注意点もあります。
香りを抑えすぎると、今度は人間にとっても魅力が半減してしまうんです。
「せっかく育てたのに、おいしくない…」なんてことにならないよう、バランスが大切です。
結論として、スイカの香りは大切ですが、ハクビシン対策としては「適度に抑える」ことが重要です。
完全に消すのではなく、うまく管理することで、美味しさも保ちつつハクビシンの被害も減らせるんです。
「今年こそは香り高いスイカを自分で食べるぞ!」という方、ぜひこの方法を試してみてください。
きっと、スイカ栽培の新たな楽しみ方を発見できるはずですよ。
収穫時期の調整で「被害リスク」を軽減する方法
収穫時期をうまく調整することで、ハクビシンの被害リスクを大きく減らせることをご存知ですか?実は、収穫のタイミングがハクビシン対策の重要なポイントなんです。
まず、通常の収穫時期について考えてみましょう。
「完熟してから収穫するのが一番おいしいでしょ?」と思う方も多いはず。
でも、その完熟を狙ってハクビシンもやってくるんです。
通常の収穫時期に潜む危険性は3つあります。
- 完熟すると香りが強くなり、ハクビシンを引き寄せやすい
- 糖度が上がることで、ハクビシンにとって魅力的な餌になる
- 収穫適期の幅が狭いため、タイミングを逃すとすぐに被害にあう
ここで重要なのが、収穫時期の「前倒し」です。
少し早めに収穫することで、ハクビシンの被害を大幅に減らせる可能性が高いんです。
収穫時期を早める方法とそのメリットは以下の通りです。
- つるが枯れ始めたら収穫する(完熟の1週間ほど前)
- たたいた音が「ポン」と響いたら収穫する(少し早めだが十分美味しい)
- 朝露がついているうちに収穫する(ハクビシンの活動時間外)
でも、ご安心ください。
スイカは収穫後も熟成が進むんです。
室内で数日置くことで十分な甘さと風味が出るんです。
「ちょっと早めに収穫したけど、これはこれでおいしい!」と驚く方も多いはずです。
ただし、注意点もあります。
早すぎる収穫は逆効果です。
未熟なスイカは味が落ちるだけでなく、日持ちも悪くなってしまいます。
「せっかく早く収穫したのに、すぐにダメになっちゃった…」なんてことにならないよう、適切なタイミングを見極めることが大切です。
結論として、収穫時期を少し早めることで、ハクビシンの被害リスクを大きく軽減できます。
完熟を待つよりも、安全に収穫できる喜びの方が大きいはずです。
「今年こそは全部自分で食べるぞ!」という方、ぜひこの方法を試してみてください。
きっと、新しいスイカ栽培の楽しみ方を発見できるはずですよ。
意外と簡単!スイカ畑のハクビシン対策アイデア
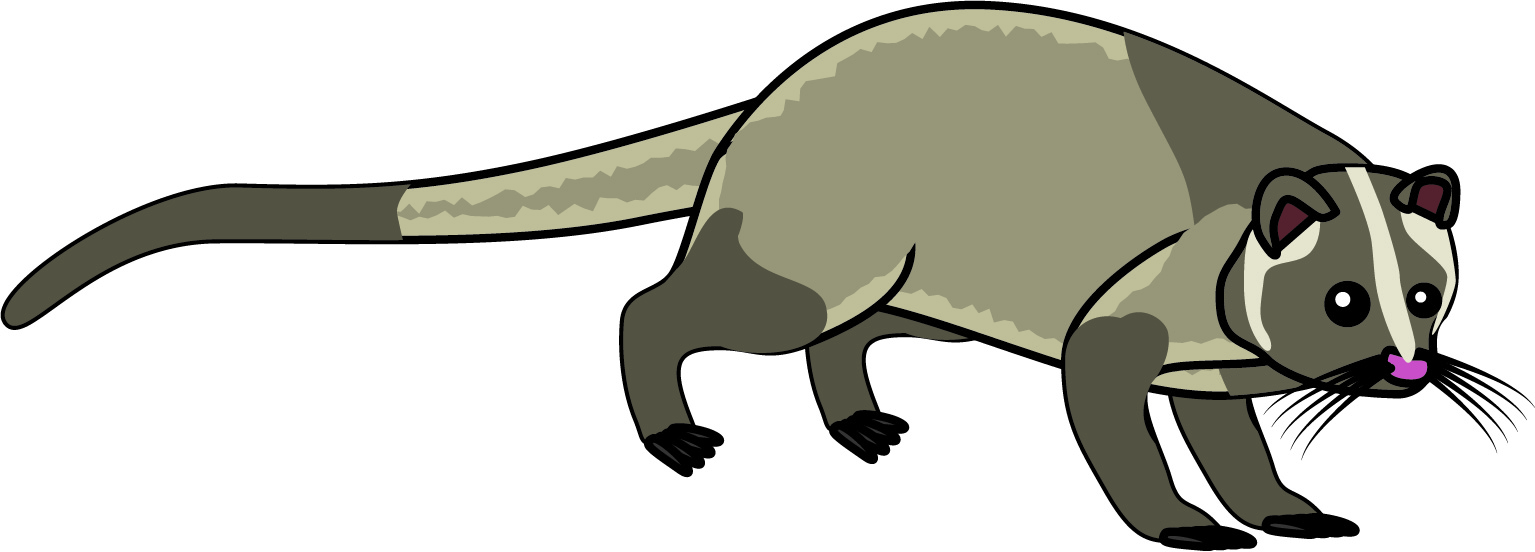
スイカの周りに「キュウリの囮」を植える作戦
スイカの周りにキュウリを植えると、ハクビシンの被害を軽減できるんです。意外かもしれませんが、これはとても効果的な方法なんですよ。
なぜキュウリなのか、不思議に思う方もいるでしょう。
実はハクビシンは、スイカよりもキュウリの方が大好きなんです。
「えっ、そうなの?」と驚く方も多いはず。
キュウリの方が食べやすく、香りも強いため、ハクビシンにとっては魅力的な食べ物なんです。
この方法には、いくつかのポイントがあります。
- キュウリをスイカ畑の外周に植える
- キュウリの数はスイカの3分の1程度が目安
- キュウリは収穫せず、ハクビシン用に残しておく
確かにそうなんですが、ここがミソなんです。
キュウリを食べている間に、スイカを守る時間が稼げるんです。
この方法のメリットは、自然な形でハクビシンを誘導できること。
農薬や化学物質を使わないので、環境にも優しいんです。
「一石二鳥だね!」とニッコリ。
ただし、注意点もあります。
キュウリの世話も必要になるので、手間は少し増えます。
でも、「スイカを守るためなら、頑張れる!」という気持ちで取り組んでみてください。
この方法を試した人の中には、「キュウリだけ食べられて、スイカは無事だった」という声も。
まさに「囮作戦成功!」というわけです。
皆さんも、ぜひ試してみてはいかがでしょうか?
使用済み猫砂で「ハクビシン撃退」の効果を検証
使用済みの猫砂をスイカ畑の周りに撒くと、ハクビシンを撃退できるって知っていましたか?これ、意外と効果があるんです。
なぜ猫砂なのか、不思議に思うかもしれません。
実はハクビシンは、猫の匂いを嫌うんです。
「え?そんな簡単なことで効果があるの?」と驚く方も多いはず。
でも、これが意外とハクビシン対策の強い味方になるんです。
この方法を使う際のポイントは3つあります。
- 使用済みの猫砂を畑の周りに均等に撒く
- 雨が降った後は再度撒き直す
- 2週間に1回程度、新しい猫砂に交換する
ご安心ください。
猫を飼っている友人や近所の方に、使用済みの猫砂を分けてもらうのもいいアイデアです。
「ちょっと恥ずかしいけど、スイカのためだもんね」と勇気を出して頼んでみましょう。
この方法のメリットは、手軽で費用がかからないこと。
特別な道具も必要ありません。
「簡単なのに効果があるなんて、すごいね!」とびっくり。
ただし、注意点もあります。
猫砂の匂いが強いと、近所の方に迷惑をかける可能性があります。
適度な量を守り、周囲への配慮も忘れずに。
この方法を試した人の中には、「ハクビシンの姿を見なくなった」という声も。
まさに「猫の力で勝利!」というわけ。
皆さんも、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか?
匂いは気になるかもしれませんが、おいしいスイカを守るためなら頑張れるはずです。
風車やラジオの設置で「不快な環境」を演出
風車やラジオを使ってハクビシンを追い払う方法があるんです。これ、意外と効果的なんですよ。
なぜ風車やラジオなのか、疑問に思う方もいるでしょう。
実はハクビシンは、予期せぬ動きや音が苦手なんです。
「え?そんな簡単なもので効果があるの?」と驚く方も多いはず。
でも、これがハクビシン対策の強力な武器になるんです。
この方法を実践する際のポイントは3つあります。
- 風車は畑の四隅に設置する
- ラジオは夜間のみ、低音量で流す
- 定期的に位置や音源を変える
その心配はもっともです。
ラジオの音量は本当に小さくし、深夜は使用を控えるなど、周囲への配慮を忘れずに。
「ご近所さんとの関係も大切だもんね」と、バランスを取りながら対策を進めましょう。
この方法のメリットは、設置が簡単で費用も抑えられること。
特別な技術も必要ありません。
「家にあるもので対策できるなんて、助かるね!」とホッとする方も多いはず。
ただし、注意点もあります。
ハクビシンが慣れてしまう可能性があるので、定期的に tactics を変えることが大切です。
「よし、今日はこっちの作戦!」と、いろいろ試してみるのも楽しいですよ。
この方法を試した人の中には、「ハクビシンの訪問が激減した」という声も。
まさに「音と動きで勝利!」というわけです。
皆さんも、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
ちょっとした工夫で、大切なスイカを守れるかもしれません。
がんばって対策、楽しんでくださいね。
反射板や風鈴で「ハクビシンを警戒」させる工夫
反射板や風鈴を使ってハクビシンを警戒させる方法があるんです。これ、意外と効果的なんですよ。
なぜ反射板や風鈴なのか、不思議に思う方もいるでしょう。
実はハクビシンは、突然の光や音に敏感なんです。
「え?そんな簡単なもので効果があるの?」と驚く方も多いはず。
でも、これがハクビシン対策の強力な味方になるんです。
この方法を実践する際のポイントは3つあります。
- 反射板は月明かりや街灯の光を反射するよう設置
- 風鈴は畑の周りに複数個つるす
- 定期的に位置を変えて、慣れを防ぐ
その心配はよくわかります。
反射板は小さめのものを選び、風鈴は可愛いデザインのものを使うなど、見た目にも配慮しましょう。
「畑が素敵になるなら一石二鳥だね!」と、前向きに捉えてみるのもいいですね。
この方法のメリットは、設置が簡単で費用も抑えられること。
特別な技術も必要ありません。
「家にあるもので対策できるなんて、助かるわ!」とホッとする方も多いはず。
ただし、注意点もあります。
強風の日は風鈴の音が大きくなる可能性があるので、天候に応じて調整が必要です。
「今日は風が強いから、風鈴を外しておこう」と、こまめな対応が大切です。
この方法を試した人の中には、「ハクビシンの足跡が減った」という声も。
まさに「光と音で勝利!」というわけ。
皆さんも、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
ちょっとした工夫で、大切なスイカを守れるかもしれません。
がんばって対策、楽しんでくださいね。
スイカに「目玉模様」を描いて天敵に見せかける策
スイカに目玉模様を描いてハクビシンを撃退する方法があるんです。これ、ちょっと変わってるけど、意外と効果があるんですよ。
なぜ目玉模様なのか、不思議に思う方もいるでしょう。
実はハクビシンは、大きな目を持つ動物を天敵と認識する傾向があるんです。
「え?そんな単純なことで効果があるの?」と驚く方も多いはず。
でも、これがハクビシン対策の意外な切り札になるんです。
この方法を実践する際のポイントは3つあります。
- 食用色素を使って、大きな目玉模様を描く
- 目玉はできるだけリアルに、怖そうに描く
- 雨で消えたら描き直す
ご安心ください。
食用色素を使えば、食べる時に洗い流せます。
「ちょっと面白いけど、効果があるなら試してみよう!」と、遊び心を持って取り組んでみましょう。
この方法のメリットは、費用がほとんどかからず、誰でも簡単にできること。
芸術センスは関係ありません。
「へたくそな絵でも効果があるなんて、うれしいな!」と喜ぶ方も多いはず。
ただし、注意点もあります。
あまりにも怖い目玉を描くと、収穫時に自分が驚いてしまう可能性も。
「うわっ!」と思わずビックリしないよう、程よい怖さを心がけましょう。
この方法を試した人の中には、「ハクビシンの被害が減った」という声も。
まさに「目は心の窓、ハクビシンの心も動かす」というわけです。
皆さんも、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
ちょっとした遊び心で、大切なスイカを守れるかもしれません。
がんばって対策、楽しんでくださいね。