ハクビシンはどこから入る?【5cmの隙間があれば侵入可能】侵入を防ぐ5つの家屋改善策

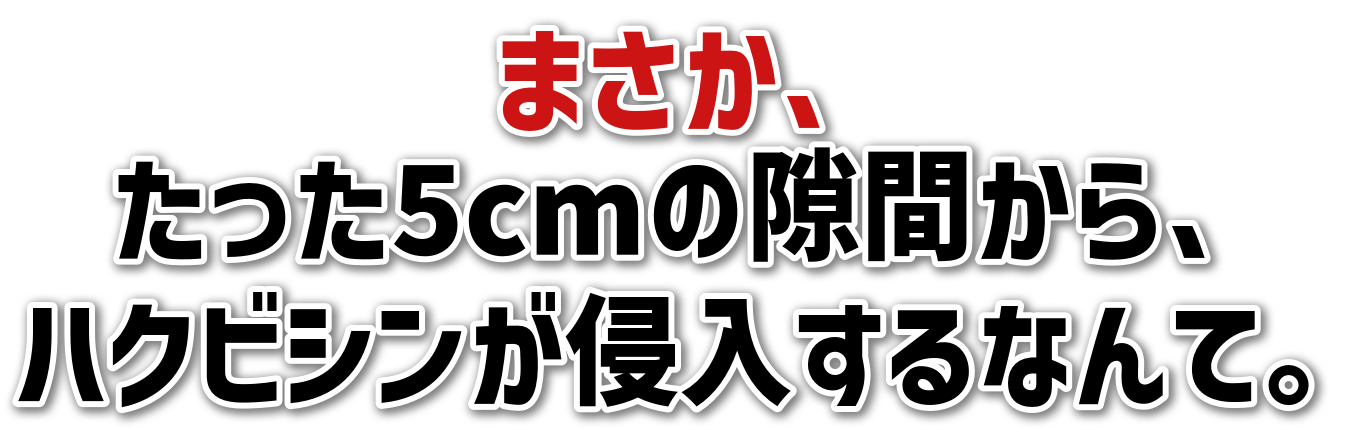
【この記事に書かれてあること】
家の中にハクビシンが侵入して困っていませんか?- ハクビシンはわずか5cmの隙間から侵入可能
- 屋根裏や換気口が主な侵入経路
- 古い家屋ほど侵入リスクが高い
- 季節や建物の種類により侵入経路が変化
- 簡単な対策で効果的にハクビシンを撃退可能
実は、ハクビシンはわずか5センチの隙間があれば侵入できてしまうんです。
「えっ、そんな小さな隙間から?」と驚く方も多いはず。
でも、ご安心ください。
この記事では、ハクビシンの侵入経路と、誰でも簡単にできる10の対策方法をご紹介します。
屋根裏や換気口、壁の亀裂など、家のどこが狙われやすいのか、そして身近なもので作れる驚きの防御方法まで、詳しく解説していきます。
さあ、一緒にハクビシン対策を始めましょう!
【もくじ】
ハクビシンはどこから侵入する?5cmの隙間に要注意

ハクビシンが通れる隙間は「わずか5cm」の衝撃!
ハクビシンはなんと、たった5cmの隙間さえあれば侵入できてしまうのです!「え?そんな小さな隙間から入れるの?」と驚かれる方も多いでしょう。
でも、本当なんです。
ハクビシンの体は意外とくにゃくにゃしていて、骨格が柔軟なんです。
そのため、頭が通れる隙間なら体全体を通すことができるんです。
「まるでスクワットマンみたい!」と言えば分かりやすいでしょうか。
では、どんな場所に5cmの隙間ができやすいのでしょうか?
よくあるのは次のような場所です。
- 屋根瓦のずれた部分
- 壁と屋根の接合部
- 古くなって緩んだ換気口
- 劣化した外壁のひび割れ
- 配管や電線の通り道
実は、築年数が経った家ほど、こういった隙間ができやすいんです。
木材の収縮や建物の歪みで、気づかないうちに隙間ができていることもあります。
ハクビシンにとって5cmの隙間は「ようこそ」の看板のようなもの。
「ここから入れそう!」とピンときちゃうんです。
だから、家の外周りをよく観察して、小さな隙間も見逃さないことが大切です。
「えっ、こんな小さな隙間でも?」と思うような場所こそ、要注意なんですよ。
屋根裏や換気口が「侵入経路ランキング」上位に
ハクビシンの侵入経路、知っていますか?実は、屋根裏と換気口が侵入経路ランキングのトップを争うんです!
「えっ、そんな高いところから?」と思われるかもしれません。
でも、ハクビシンは木登りの達人。
高いところなんて平気なんです。
では、屋根裏や換気口が狙われやすい理由を見ていきましょう。
- 屋根裏の魅力
- 暗くて静か
- 人目につきにくい
- 温かい空間
- 換気口の魅力
- 直接室内へつながる
- 比較的広い開口部
- 格子状で登りやすい
特に注意が必要なのは、屋根の端や軒下の部分。
ここは屋根と壁が接する場所で、経年劣化で隙間ができやすいんです。
ハクビシンはここをよじ登って、屋根裏へ侵入しちゃうんです。
換気口も要注意です。
特に格子状の換気口は、ハクビシンにとっては快適な階段。
すいすいと登って侵入されちゃいます。
「まるでジャングルジムだね」なんて言いたくなるくらいです。
対策としては、定期的な点検がおすすめ。
屋根や換気口の周りに不自然な傷や隙間がないか、チェックしてみましょう。
「ちょっとした隙間くらい…」なんて油断は禁物です。
ハクビシンにとっては、それが立派な玄関になっちゃうんです。
古い家屋ほど「侵入リスクが高い」理由とは
古い家屋ほどハクビシンの侵入リスクが高いって知っていましたか?「えっ、うちの家大丈夫かな…」なんて心配になっちゃいますよね。
でも、なぜ古い家屋がハクビシンに狙われやすいのか、その理由をしっかり押さえておけば対策も立てやすくなります。
古い家屋が侵入されやすい主な理由は、次の3つです。
- 建材の劣化:長年の風雨にさらされて、木材が腐ったり、金属部分が錆びたりします。
- 構造のゆがみ:地盤の沈下や建物の重みで、少しずつ歪みが生じます。
- リフォーム痕:過去の改修工事で、思わぬ隙間ができていることも。
「まるで、ハクビシン用の秘密の抜け道みたい!」なんて冗談も言えないくらいです。
特に注意が必要なのは、屋根と外壁の接合部。
ここは雨風の影響を受けやすく、劣化が進みやすい場所なんです。
「えっ、そんなところまでチェックするの?」と思われるかもしれません。
でも、ハクビシンはそんな細かい隙間も見逃しませんよ。
また、古い家屋特有の「すきま風」にも要注意。
冬に「ヒュー」っと風が入ってくる場所があれば、そこはハクビシンの侵入口になる可能性大です。
「ああ、あそこか!」って思い当たる場所はありませんか?
対策としては、定期的なメンテナンスが一番。
特に屋根や外壁は、プロに点検してもらうのがおすすめです。
「ちょっとした隙間」を放っておくと、それがハクビシンの立派な玄関になっちゃうんです。
古い家屋だからこそ、こまめなケアが大切ですよ。
ハクビシン侵入を「誘発する環境」に要注意!
ハクビシンの侵入、実は私たちが知らず知らずのうちに誘発しているかもしれないんです。「えっ、そんなことあるの?」と驚く方も多いでしょう。
でも、ハクビシンを引き寄せてしまう環境要因があるんです。
ハクビシンを誘発する環境、主に次の3つがあります。
- 餌場となる場所
- 生ゴミの放置
- 果樹園や家庭菜園
- ペットフードの野外放置
- 隠れ家になる場所
- 木の茂み
- 物置や倉庫
- 積みっぱなしの資材
- 水場
- 池や小川
- 雨水がたまりやすい場所
- ペットの水飲み場
これらの環境は、ハクビシンにとっては「ようこそ」の看板を出しているようなものなんです。
特に注意したいのが、果樹や野菜の栽培。
ハクビシンは果物や野菜が大好き。
「せっかく育てた野菜が…」なんて悲しい結果にならないよう、収穫物はしっかり守りましょう。
また、家の周りの整理整頓も大切。
物が散らかっていると、ハクビシンの絶好の隠れ家に。
「ちょっと片付けるだけでいいの?」と思うかもしれません。
でも、これが意外と効果的なんです。
水場の管理も忘れずに。
ハクビシンは水を求めてやってくることも。
「え、水まで気にしないと?」と驚くかもしれませんが、生き物にとって水は命綱。
だからこそ、不要な水たまりはなくしましょう。
環境を整えるだけで、ハクビシンの侵入リスクをグッと下げられます。
「よし、今日から庭の整理整頓だ!」なんて意気込んでみるのも良いかもしれませんね。
「5cmの隙間塞ぎ」はやっちゃダメ!逆効果の理由
ハクビシンの侵入口、見つけたらすぐに塞ぎたくなりますよね。でも、ちょっと待って!
5cmの隙間を見つけて「よし、これを塞いじゃえ!」なんて思ったら大間違い。
実は、これが逆効果になることがあるんです。
なぜ、5cmの隙間を塞ぐのがダメなのか。
理由は主に3つあります。
- 新たな侵入口を作ってしまう:慌てて塞ぐと、別の場所に新しい隙間ができることも。
- 中にいるハクビシンを閉じ込める:外にいると思って塞いだら、実は中にいて出られなくなることも。
- 一時的な対策にしかならない:根本的な原因を解決しないと、また同じ場所に隙間ができやすい。
でも、本当なんです。
特に注意したいのは、2番目の「閉じ込め」問題。
ハクビシンを家の中に閉じ込めてしまうと、パニックになって家の中を荒らしてしまうかもしれません。
「うわっ、それは大変!」ですよね。
また、慌てて隙間を塞ぐと、別の場所に新たな隙間を作ってしまうことも。
「もぐらたたきみたいだな」なんて言いたくなりますが、本当にそんな感じになっちゃうんです。
では、どうすればいいのでしょうか?
まずは、ハクビシンが本当にいなくなったことを確認すること。
そして、専門家に相談して適切な対策を立てることが大切です。
例えば、一方通行の出口を作って、中にいるハクビシンを外に誘導する方法があります。
「へえ、そんな方法があるんだ!」と驚く方も多いでしょう。
結局のところ、5cmの隙間対策は慎重に行う必要があるんです。
「急いては事を仕損じる」ということわざがありますが、まさにその通り。
焦らず、適切な対策を取ることが、長期的には一番の近道なんです。
ハクビシンの侵入経路を徹底比較!弱点を知って対策
屋根裏vs換気口「どちらが侵入されやすい?」
屋根裏と換気口、どちらがハクビシンに侵入されやすいでしょうか?結論から言うと、屋根裏の方が侵入されやすいんです。
屋根裏は、ハクビシンにとって魅力的な場所なんです。
なぜかというと、次のような特徴があるからです。
- 暗くて静か
- 温かい
- 人目につきにくい
- 広々としている
一方、換気口はどうでしょうか。
確かに侵入経路として使われることはありますが、屋根裏ほど頻繁ではありません。
換気口の特徴は次のとおりです。
- 開口部が比較的小さい
- 人の気配を感じやすい
- 風の流れがある
「うちの換気口、大丈夫かな?」と心配になった方、ちょっと確認してみましょう。
古い換気口は劣化して隙間が大きくなっていることがあるんです。
屋根裏への侵入を防ぐには、屋根と壁の接合部をよくチェックすることが大切です。
小さな隙間も見逃さないように、じっくり点検しましょう。
「えっ、こんな小さな隙間でも?」と思うかもしれませんが、ハクビシンは5センチの隙間さえあれば入り込めるんです。
びっくりですよね。
換気口の対策としては、細かいメッシュのカバーを取り付けるのが効果的です。
これで、ハクビシンの侵入をぐっと防げます。
「よし、明日にでもホームセンターに行こう!」そんな気持ちになりますよね。
どちらの場所も、定期的なチェックと適切な対策が重要です。
家の弱点を知って、しっかり守りましょう。
壁の亀裂vs配管周り「侵入経路の危険度」を比較
壁の亀裂と配管周り、どちらがハクビシンの侵入経路として危険なのでしょうか?実は、配管周りの方が危険度が高いんです。
まず、壁の亀裂について見てみましょう。
確かに、亀裂は侵入経路になる可能性はあります。
でも、次のような特徴があります。
- 目につきやすい
- 修理しやすい
- 亀裂が小さいことが多い
一方、配管周りはどうでしょうか。
実は、これがかなり要注意なんです。
配管周りの特徴は次のとおりです。
- 目につきにくい場所にある
- 家の内外をつなぐ直接的な経路になる
- 隙間が大きくなりやすい
配管周りが危険な理由は、家の中と外をつなぐ「トンネル」のような役割を果たしてしまうからなんです。
ハクビシンにとっては、まさに「ようこそ」の看板がついているようなものです。
特に注意が必要なのは、次のような場所です。
- 台所の排水管周り
- 浴室の換気扇周り
- エアコンの配管周り
「うわっ、うちにもそんな場所あるかも...」なんて思い当たる方も多いのではないでしょうか。
対策としては、配管周りの隙間をしっかり埋めることが大切です。
専用の充填材を使って、きれいに塞いでしまいましょう。
「よし、週末にでも点検だ!」そんな気持ちになりますよね。
壁の亀裂も油断は禁物ですが、配管周りにはより注意を払う必要があります。
家のあちこちをよくチェックして、ハクビシンの侵入を防ぎましょう。
新築vs築古「ハクビシンに狙われやすいのはどっち?」
新築と築古の家、どちらがハクビシンに狙われやすいと思いますか?結論から言うと、築古の家の方が圧倒的に狙われやすいんです。
まず、新築の家の特徴を見てみましょう。
- 建材が新しく、隙間が少ない
- 設計が現代的で、侵入されにくい構造
- 防虫網や換気口のカバーが新しい
でも、ちょっと待ってください。
新築だからといって、完全に安全というわけではないんです。
一方、築古の家はどうでしょうか。
実は、ハクビシンにとっては「お気に入りスポット」なんです。
築古の家の特徴は次のとおりです。
- 経年劣化で隙間が多い
- 屋根や外壁に傷みがある
- 古い設計で、侵入されやすい構造
- リフォームの跡が新たな侵入口に
築古の家が狙われやすい理由は、時間とともに家全体が「すきま darake」になってしまうからなんです。
小さな隙間が少しずつ大きくなり、気づいたらハクビシンにとっての「welcome」看板になっているんです。
特に注意が必要なのは、次のような場所です。
- 屋根と壁の接合部
- 軒下や破風板の周り
- 古い換気口や通気口
- 雨樋の取り付け部分
「そういえば、そんな場所、最近点検してないな...」なんて思い当たる方も多いのではないでしょうか。
対策としては、定期的な点検と修繕が欠かせません。
小さな傷みも見逃さず、早めに対処することが大切です。
「よし、明日からこまめにチェックしよう!」そんな気持ちになりますよね。
新築の家も油断は禁物ですが、築古の家はより一層の注意が必要です。
家の年齢に関わらず、こまめなケアでハクビシンの侵入を防ぎましょう。
夏vs冬「季節で変わる侵入経路」の特徴
ハクビシンの侵入経路、実は季節によって変わるんです。夏と冬では、まったく違う場所から侵入してくる可能性があります。
びっくりですよね。
まず、夏の侵入経路の特徴を見てみましょう。
- 開けっ放しの窓や網戸
- エアコンの室外機周り
- ベランダや屋上
- 庭の物置や倉庫
夏は暑さのために窓を開けがちですが、それがハクビシンにとっては絶好の侵入口になってしまうんです。
一方、冬の侵入経路はどうでしょうか。
冬は別の場所が狙われやすくなります。
- 屋根裏や壁の隙間
- 換気口や通気口
- 暖房設備の配管周り
- 雨樋や軒下
寒さをしのぐために、暖かい場所を求めてくるんです。
季節によって侵入経路が変わる理由は、ハクビシンの生態と深く関係しています。
夏は涼しい場所を、冬は暖かい場所を探しているんです。
まるで私たちと同じですよね。
特に注意が必要なのは、季節の変わり目です。
次のようなポイントに気をつけましょう。
- 春:繁殖期に入るので、巣作りのために侵入を試みる
- 夏:暑さを避けて日陰や涼しい場所を探す
- 秋:冬に備えて食料を探し、侵入が増える
- 冬:寒さを避けて暖かい屋内に侵入しようとする
対策としては、季節に合わせた点検と対策が重要です。
夏は窓や網戸の確認を、冬は屋根裏や壁の隙間のチェックを重点的に行いましょう。
「よし、カレンダーに点検日を書き込もう!」そんな気持ちになりますよね。
季節によって変わる侵入経路を知ることで、より効果的な対策が可能になります。
四季折々の対策で、ハクビシンの侵入をしっかり防ぎましょう。
戸建てvsマンション「ハクビシン被害の違い」
戸建てとマンション、ハクビシンの被害にどんな違いがあるのでしょうか?実は、両方とも被害に遭う可能性があるんです。
でも、その特徴は大きく異なります。
まず、戸建ての被害の特徴を見てみましょう。
- 屋根裏への侵入が多い
- 庭や物置が被害に遭いやすい
- 家全体が侵入対象になる
- 個別の対策が必要
確かに、戸建ては家全体を守る必要があるので、対策が大変です。
一方、マンションの被害はどうでしょうか。
意外かもしれませんが、マンションでも被害は起こります。
- ベランダからの侵入が多い
- 高層階でも被害の可能性あり
- 共用部分(屋上など)が被害に遭うことも
- 他の部屋への被害拡大の恐れ
実は、ハクビシンは垂直の壁も器用によじ登れるんです。
まるでスパイダーマンのようですね。
戸建てとマンションで被害の特徴が異なる理由は、建物の構造の違いにあります。
戸建ては地面から屋根まで連続した構造なので、侵入経路が多様です。
一方、マンションは縦に積み重なった構造なので、ベランダや外壁が主な侵入経路になります。
特に注意が必要なのは、次のような場所です。
- 戸建て:屋根と外壁の接合部、換気口、物置
- マンション:ベランダの隅、エアコンの配管周り、ゴミ置き場
対策としては、建物タイプに合わせたアプローチが必要です。
戸建ては家全体の点検と修繕を、マンションはベランダや窓周りの重点的な対策を行いましょう。
「よし、明日からさっそく始めよう!」そんな気持ちになりますよね。
戸建てもマンションも、それぞれの特徴を理解して対策を立てることが大切です。
建物タイプに関わらず、日頃からの注意と適切な対策で、ハクビシンの被害から家を守りましょう。
「うちはマンションだから大丈夫」なんて油断は禁物です。
どちらの住居タイプでも、ハクビシン対策は必要なんです。
定期的な点検と、早めの対応が鍵になります。
「今日からもっと家のことに気を配ろう」そんな気持ちになりませんか?
結局のところ、戸建てもマンションも、住人の意識が最大の防御になるんです。
ハクビシンの習性を知り、自分の家の弱点を把握することで、より効果的な対策が可能になります。
一緒に、ハクビシンのいない快適な住環境を作っていきましょう。
5cmの隙間対策!簡単・即効性のある防御方法5選

ペットボトルで作る「即席侵入防止装置」の作り方
ペットボトルを使って、ハクビシンの侵入を防ぐ簡単な装置が作れるんです。これ、意外と効果があるんですよ。
まず、必要なものは次の3つだけです。
- 2リットルのペットボトル
- はさみ
- ガムテープ
ペットボトルを半分に切って、切り口を外側に向けて侵入口に取り付けるだけ。
「えっ、そんな簡単なの?」って思いますよね。
でも、これがなかなかの優れもの。
ハクビシンは賢い動物ですが、この不思議な形の障害物に出くわすと、「何これ?」ってびっくりしちゃうんです。
ペットボトルの滑らかな表面は登りにくいし、鋭い切り口は触るのを躊躇させる。
まるで、ハクビシン用の「立入禁止」の看板みたいなものです。
取り付け方のコツは、ペットボトルの口を下に向けることです。
こうすると、雨水がたまりにくくなります。
「なるほど、そういう工夫があったんだ」って感心しちゃいますよね。
この方法の良いところは、材料が身近にあることです。
「今すぐにでも始められそう!」って思いませんか?
しかも、お金もほとんどかからない。
まさに、エコでお財布に優しい対策方法です。
ただし、注意点もあります。
強風で飛ばされないように、しっかりとガムテープで固定すること。
それから、定期的に点検して、劣化したら新しいものに交換するのを忘れずに。
「よし、週末にでも作ってみよう!」そんな気持ちになりませんか?
LEDライト+人感センサーで「ハクビシン撃退」
思わず目を見張るほど効果的なハクビシン対策、それがLEDライトと人感センサーの組み合わせなんです。これ、本当によく効くんですよ。
まず、この方法の仕組みを簡単に説明しましょう。
- 人感センサーがハクビシンの動きを感知
- センサーが作動してLEDライトが点灯
- 突然の明るさにハクビシンがびっくり
- 怖がって逃げ出す
でも、これが意外とハクビシンには効果絶大なんです。
ハクビシンは夜行性の動物です。
暗闇の中でゆっくり行動しているところに、突然まぶしい光が当たったら、びっくりしちゃいますよね。
まるで、真夜中に寝ている時に突然電気をつけられたような感覚かもしれません。
「うわっ、まぶしい!」って感じです。
この方法の良いところは、設置が簡単なこと。
ホームセンターで材料を買ってきて、侵入口の近くに取り付けるだけ。
「よし、これなら私にもできそう!」って思いませんか?
ただし、注意点もあります。
LEDライトの向きは重要です。
ハクビシンの目線の高さに合わせて、直接顔に光が当たるようにしましょう。
それから、バッテリー切れにも注意が必要です。
「あれ?昨日まで効いていたのに...」なんてことにならないように、定期的にチェックするのを忘れずに。
この方法、実は省エネでエコな対策なんです。
LEDライトは消費電力が少ないし、人感センサーのおかげで必要な時だけ点灯します。
「ハクビシン対策しながら、電気代も節約できるなんて一石二鳥だね!」そんな風に思いませんか?
古いCDで作る「反射板」でハクビシンを威嚇
使い道のなくなった古いCDが、実はハクビシン対策の強い味方になるんです。これ、意外と効果があるんですよ。
CDを使った反射板の作り方は、とっても簡単です。
- 古いCDを集める
- CDに紐を通す穴を開ける
- 紐を通して結ぶ
- 侵入口の近くに吊るす
でも、これがなかなかの効果を発揮するんです。
CDの表面は、きらきらと光を反射します。
これが風で揺れると、あちこちに光が散らばるんです。
まるで、ディスコボールのよう。
「わぁ、きれい!」って思うかもしれませんが、ハクビシンにとっては全然きれいじゃありません。
ハクビシンは、突然の光の変化に敏感なんです。
暗闇の中で動いているときに、急に光がちかちかすると、びっくりしちゃうんですね。
「うわっ、何これ?」って感じで警戒心が強くなります。
この方法の良いところは、お金がほとんどかからないこと。
家にある古いCDを再利用できるので、エコにもなります。
「よし、押し入れの奥にあったCDを引っ張り出してこよう!」そんな気持ちになりませんか?
ただし、注意点もあります。
CDの表面に傷がついていると、反射効果が弱くなります。
それから、強風で飛ばされないように、しっかりと固定することも大切です。
「そうか、こんなところにも気をつけないとね」って感じですよね。
この方法、実はハクビシン以外の動物にも効果があるんです。
鳥や猫なども、きらきら光る物が苦手。
「一石二鳥どころか、一石三鳥?」なんて思っちゃいますね。
使用済み茶葉の「香りバリア」で寄せ付けない工夫
お茶を飲んだ後の使用済み茶葉、実はハクビシン対策に大活躍するんです。これ、意外と効果があるんですよ。
使用済み茶葉を使った「香りバリア」の作り方は、とってもシンプル。
- 使用済みの茶葉を集める
- 天日で完全に乾燥させる
- 侵入口の周りに散布する
でも、これがなかなかの効果を発揮するんです。
茶葉には独特の香りがあります。
私たち人間にとっては、お茶の良い香りに感じるかもしれません。
でも、ハクビシンにとっては全然良い香りじゃないんです。
むしろ、「うわっ、この匂い苦手!」って感じで避けたがります。
特に効果的なのは、緑茶や烏龍茶の茶葉です。
これらには、ハクビシンが苦手とする成分が含まれているんです。
「へえ、お茶の種類によっても効果が違うんだ」って驚きますよね。
この方法の良いところは、お金がかからないこと。
毎日飲むお茶の茶葉を再利用できるので、エコにもなります。
「よし、今日からお茶の茶葉を捨てずに取っておこう!」そんな気持ちになりませんか?
ただし、注意点もあります。
茶葉は湿気を吸いやすいので、必ず完全に乾燥させること。
それから、雨で流されないように、定期的に散布し直すことも大切です。
「そうか、こまめなケアが必要なんだね」って感じですよね。
この方法、実は虫除けにも効果があるんです。
蚊やアリなども、お茶の香りが苦手。
「一石二鳥どころか、一石三鳥?」なんて思っちゃいますね。
家の周りがいい香りになって、ハクビシン対策もできる。
素敵な方法だと思いませんか?
風船を使った「簡易アラーム」の設置方法
風船がハクビシン対策に使えるって、信じられますか?実は、これがなかなか効果的なんです。
風船を使った「簡易アラーム」の作り方、ご紹介しますね。
まず、必要なものは次の3つだけです。
- 風船
- 紐
- 画鋲やテープ(固定用)
- 風船を膨らませる
- 風船に紐を結ぶ
- 紐の反対側を侵入口近くに固定する
でも、これが意外と効果があるんです。
仕組みはこうです。
ハクビシンが侵入しようとして風船に触れると、「パン!」と大きな音がします。
この突然の音にハクビシンはびっくり仰天。
「うわっ、何これ!?」って感じで、逃げ出しちゃうんです。
この方法の良いところは、材料が安くて手に入りやすいこと。
「今すぐにでも始められそう!」って思いませんか?
しかも、設置も簡単です。
ただし、注意点もあります。
風船は時間が経つとしぼんでしまうので、定期的に新しいものと交換する必要があります。
それから、強風で飛ばされないように、しっかりと固定することも大切です。
「そうか、こまめなケアが必要なんだね」って感じですよね。
この方法、実は他の動物対策にも使えるんです。
猫や野鳥なども、突然の音が苦手。
「一石二鳥どころか、一石三鳥?」なんて思っちゃいますね。
風船アラームは、見た目も楽しいですよ。
カラフルな風船を使えば、ハクビシン対策しながら、お庭の雰囲気も明るくなります。
「よし、今度の週末にやってみよう!」そんな気持ちになりませんか?
家族で協力して作れば、楽しい時間にもなりそうです。